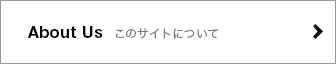今から約10年前、マイクロこと元CT選手のグレン・ホール辺りからCTで定着してきたサーフィンのコーチという存在。
それまでもコーチを付けていた選手はいたものの、マイクロは長年トップ10圏外だったマット・ウィルキンソンを、ワールドタイトルを現実的に狙えるレベルまで引き上げ、タイラー・ライトの2Xにも大きく貢献。
一時はスーパーコーチという称号まで与えられ、ここからサーフィンのコーチングというシステムが大きく取り上げられるようになった。
マイクロの他にもジョン・ジョン・フローレンスをタイトルに導いたロス・ウィリアムスをはじめ、ジェイク・パターソンやマイク・パーソンズ、トム・ウィタカー、ドッグことリチャード・マーシュ、ルーク・イーガン、エイドリアーノ・デ・スーザなど元CT選手が経験を活かしてコーチになるケースが多く、それが成功に結び付いた例も多い。

また、コーチは戦略的、技術的な面はもちろんのこと、サーフィンコンテストで重要なメンタル面の支えとしても大きな役割を担っている。
例えば、スネークことジェイク・パターソンに長年指導を受けている五十嵐カノアは、スネークの豊富な経験を深く信頼しており、その存在が精神的な支えにもなっているという。選手のコーチングは、コーチ自身の知識経験に加え、選手との相性も重要だ。
日本にも広がるコーチング文化
こうした海外でのコーチング文化の成熟は、日本国内にも広がりつつある。近年では、多くのプロサーファーを指導して実績もある浦山哲也をはじめ、大野修聖、田中樹、田中英義、田嶋鉄兵など、日本のサーフィン界を支えてきた人物が、豊富な経験をもとにコーチングの現場で活躍している。現役選手らが自身のヒートの合間に若手選手をサポートする光景も多く見られるようになった。また、河村海沙のように、現地でのサポートを含むコーチングの一連の様子や、試合後の振り返りをYouTubeで発信するなど、一般層にもサーフィンの奥深さを伝える動きが広がっているといえるだろう。
今年9月に伊良湖で開催された国内最高グレードのQS6000「BILLABONG TAHARA PRO」では、元グランドチャンピオンの田嶋鉄兵が、鈴木莉珠、小林桂、岩見天獅、佐藤李、木津優芽のコーチを務め、鈴木莉珠が2位、小林桂が5位の好成績。
続く宮崎のQS2000では、小林桂が優勝してQSアジアリージョナルのトップに浮上。鈴木莉珠もQSアジアリージョナルで3位とCS入りを狙えるポジションにいる。


世界基準を見据えたチーム育成戦略
オリンピアンである大原洋人や松田詩野をはじめ、国内トッププロのマネジメントやQSイベントのサポートなどを行ってきた「whitebuffalo」は、その活動を通じて“世界レベルの壁”の高さを痛感してきた。
そこで日本からCT選手を輩出するための次なるステップとして、世界トップ選手のコーチングで知られる“スネーク”こと元CT選手のジェイク・パターソンにチームライダーの指導を依頼。「WSL QS6000 TAHARA PRO」の開催に合わせ、チーム独自のコーチングプログラムを実施した。
プログラムは大会6日間と開幕前合宿を含む計8日間。
日中は実戦形式のトレーニングを行い、夜はその日のライディング映像を用いた座学で課題を確認するなど、連日きめ細かな指導が続けられた。

チーム単位での利点と意義
一般的にプロサーファーのコーチングは、選手個人がそれぞれ希望するコーチへコーチングを依頼するケースが多い。
相性の良いコーチと長期的に取り組む場合もあれば、遠征先や試合ごとにスポットで依頼するケースもあるが、海外遠征など世界レベルの戦いになると、高額な旅費やコーチング費用が選手側の大きな負担となるのが現実だ。
チーム単位での活動は、経済的なメリットに加え、情報共有や戦略面での一貫性、精神的なサポートなども得やすく、結果的に選手のパフォーマンス向上へとつながりやすい。「whitebuffalo」のような組織的な取り組みは、理想的な形のひとつともいえる。


CSをチームとして戦う本格的な取り組みがスタート
今シーズン、ナショナルチーム「波乗りジャパン」は、オリンピックやISA世界選手権だけでなく、WSLのチャレンジャー・シリーズ(CS)をもチームとして戦う新たな体制を始動させた。
その内容は会場により異なるが、これまで個人での活動であったWSLイベントにもコーチ陣や専属カメラマンが帯同し、試合内容の分析や情報共有を強化。公式YouTubeなどで活動の様子を発信するなど、チーム全体で一体感を高める取り組みを行っている。
この新体制は、選手の士気向上に加え、海外での戦い方にも良い影響を与えており、実際に多くの選手が結果を残し始めている。

直近CSのポルトガル戦では田中樹、河村海沙、大村奈央がコーチとして同行。
田中樹は都筑有夢路、西慶司郎、中塩佳那、加藤翔平、田中大貴、岩見天獅を担当し、河村海沙は伊東李安琉と都築虹帆、大村奈央はROXYライダーの池田美来と佐藤李をサポートした。
一方で、大原洋人と松岡亜音はスネーク(ジェイク・パターソン)による個別コーチングを受けていたが、ヒート前後には「波乗りジャパン」の一員としてチーム全体で声援を送り合う姿も見られた。
このようなチーム一体型のサポート体制は、かつてオーストラリアやブラジルがQSやCSで成果を上げてきた要因のひとつでもある。
続くCSブラジル戦では、西慶司郎と池田美来がQFに進出し5位という結果を残した。



世界基準を見据えた次の挑戦へ
今回紹介したような取り組みは、日本サーフィン界にとって大きな進化の一歩であり、CTの舞台をより現実的な目標として捉え始めたことを示している。
個々の努力に加え、経験豊富なコーチ陣やチーム体制による支援が整いつつあり、世界基準へと少しずつ近づいているといえるだろう。
今季CSは残り2戦。来期クオリファイの可能性が残るメンバーは限られるものの、確実に結果は出始めている。その先に、日本で生まれ育ったサーファーがCT入りを果たす未来を期待したい。


(THE SURF NEWS編集部)