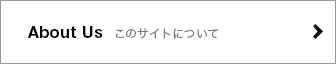神奈川県大磯町では、豊かな自然や文化に触れながら、子どもたちが「大磯の海」について学ぶ体験型プログラム「いそっこ海の教室」が、長年にわたり開催されてきた。
コロナ禍を機に休止が続いていた本活動の再開に向け、地元のローカルサーファーや海の関係者が一堂に会し、意見交換会を開催。
当日は、衆議院議員・河野太郎氏も参加し、地域と海との関わりを見つめ直し、大磯の海の未来を考える場となった。

「いそっこ海の教室」とは
大磯海岸で毎年行われてきた「いそっこ海の教室」は、主に地元の子どもたちを対象に、スノーケリングやアウトリガーカヌー、ヨットやボディボードなどを通じて、海の自然や環境を楽しく学ぶことができる自然体験プログラム。
2005年の第1回より、開催の度に100名ほどの子供たちが参加。海をもっと身近に感じ、美しい海を未来に残すという意識を育むことを目的に継続をしてきたが、コロナ禍の影響もあり2021年以降の開催は見合わせとなっていた。




再始動に向けて「海の関係者」が集結
本意見交換会には、普段から大磯の海に親しみ、ビーチの保全活動にも取り組んでいる地元ローカルサーファーをはじめ、ライフセーバーやダイバー、関連する民間事業者や観光協会、地域住民代表の方など、様々な海の関係者が参加。
「いそっこ海の教室」発足の経緯や取り組みの共有に始まり、今、大磯の海が抱える様々な課題や、今後どのように発展していくべきかの議論にも発展。様々な世代・立場からの視点で積極的な意見交換が行われた。


港の可能性と未来への取り組み
また、本会には衆議院議員・河野太郎氏も参加し、大磯港の複数のバース(船着き場)が持つ機能に言及。クルーズ船やスーパーヨットの寄港も視野に、インバウンド富裕層の受け入れに向けた環境整備を提言。
そして「大磯の海をこういう場所にしたい」というビジョンを明確に打ち出すことが今後の発展に不可欠であり、行政・住民・関係者のコンセンサス(合意形成)が必要であると強調。地域全体で海との関わりを深める文化の継承と、子どもたちが日常的に海とふれあう環境づくりの重要性を語った。


ダイビングに精通する児島氏は「いそっこ海の教室」でスノーケリングのインストラクターを担当 Photo: THE SURF NEWS
課題の共有と新たな構想
会のメンバーからは、西湘バイパス下の海岸浸食問題や、港の堤防が延長されたことでビーチに砂が付きにくくなってしまったこと、海水浴シーズンの来場者減少など、大磯の海が抱えている様々な課題も共有。
一方で、スケートパークの建設構想や、「大磯沖に沈んでいる日本製潜水艦」を観光資源として活用する案など、新たな視点も浮上。
プロライフセーバーの鯨井保年氏からは、ハワイの伝統航海カヌー「ホクレア号」受け入れ構想も語られた。

なお、町から十分な資金協力が得られない中で、ビーチの砂入れやシャワー施設の維持管理などを担ってきた大磯サーフィン協会の柏原氏からは、子供たちのスケートボード練習場として、放課後の体育館解放などを提案。
さらには、大磯港内の交流施設「OISO CONNECT(オオイソコネクト)」を利用しての情報発信などを行い、来場者の理解を深めながら、サーフィンをもっと盛り上げていきたいという思いも語られた。


地元サーファーをはじめ、様々な世代・立場の海関係者が集った今回の意見交換会。
次回開催は今秋。「いそっこ海の教室」来年の再開に向けて、準備を進めていく予定だ。
(THE SURF NEWS編集部)